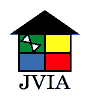本当の換気を知る第3回 換気システムの進化と限界
ベンチレーション(換気)温故知新
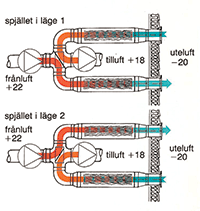
北欧に遅れることほぼ30年、日本でも2003年に建築基準法が改正され、ようやく住宅の気密化とともに24時間連続運転の機械換気設備設置のスタートラインにつき、住居容積比で毎時0.5回の換気量を確保するよう定められました。
一方で、時代は地球温暖化防止で、住宅の熱損失値をもっと小さなものにして、さらにCO2排出を下げようという運動が生まれてきました。
最近目に飛び込んでくる設備機器には「熱回収換気装置」や「ヒートポンプ暖房装置」あるいは「エコ給湯装置」などがあります。これらの機器は、従来型に対して約2倍の少々セレブ向けの値札が付けられています。
さらには、これらの熱(排気熱、空気中の熱、地中の熱、水中の熱)を回収する機器やハイブリッド設計が、従来型の先を行く「最新型の装置」としてイメージ付けされているようです。皆さんはどう考えますか?
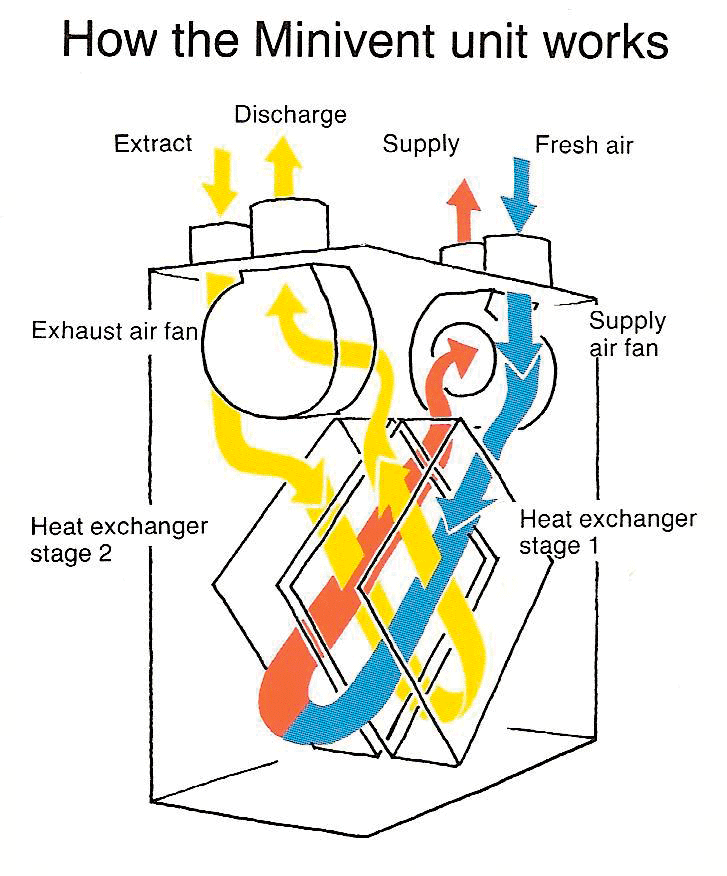
図1は、札幌市内のK社が輸入した熱回収換気(熱交換換気)システムの換気ユニットの作動図です。
アルミニウム製の熱交換素子をU字筒の両腕部に内蔵していて、このアルミ素子に排気流の熱を蓄え、次に流れが逆流に切り替わり、低温外気がアルミの熱を受け取り室内に給気される全熱交換換気装置です。
熱回収率(温度効率)は、最大95%。外気マイナス20℃でもプラス18℃で給気されるから、無暖房に迫る住宅に挑戦している人には興味がわく装置でしょう。今初めてこのような高効率製品を知った読者は、最新型の装置と思うに違いありません。
ところがこの製品、実は1978年に市販されていて、現在では既に滅び去った商品なのです。理由の一つは全熱交換の非衛生さが知られるようになったからです。
もう一つの熱回収換気装置を紹介しましょう。熱回収換気システムの換気ユニットの作動図で、アルミ製のダイヤモンド型交換素子がダブルであることが分かりますが、これは排気と給気が長い距離で触れ合うようにする狙いです(図2)。
この顕熱型熱交換素子の霜取りは、外気がマイナス4℃になると給気側が自動閉鎖される一方で排気側は作動を続け、排気熱で熱交換素子の霜取りが1時間に2回自動的に行われます。
さらに、快適性を高めたいであろう外気マイナス20℃以下に備えて、熱回収後の給気を室内温度まで加温するリヒーター(プレヒーターではない)が内蔵されており、外気が低温の場合(マイナス40℃まで運転可能)にも霜取りできるようになっています。熱回収率(温度効率)は、最高78%です。
実は図2の装置は、1980~1990年の10年間、札幌の企業が北海道内に限定して販売した顕熱回収換気システムの換気ユニットであり、現在でも多くの家庭で作動中です。
輸入元の会社はこの換気ユニットを約10年間観察して、保守の極めて簡単な換気装置であっても日本人の場合は使いっぱなしの家庭が多いことが分かり、思い切って販売を中止しました。現在人気の排気型ダクトシステムが、その後定着した理由でもあります。
熱回収効率だけ見るのは素人
1970年代に住宅用の熱回収換気システムを実用化したスウェーデンは、住宅建築の断熱・気密性能との連携を同時に研究していました。
例えば、排気型セントラル換気システムと熱回収型セントラル換気システムを建物に取り付ける場合、皆さんはどちらの換気システムが、建物に高い気密性を要求するとお考えになるでしょうか? 答えは、熱回収型換気方式の方なのです。
過去、日本の換気メーカーや学者は「熱回収セントラル換気システムは、ダクトで給気を各室に行うので気密は低くてもよい。排気型セントラル換気システムは、各室から空気を引っ張ってこなければならないのだから、こちらの方が建物に高い気密を要求する」と主張していました。
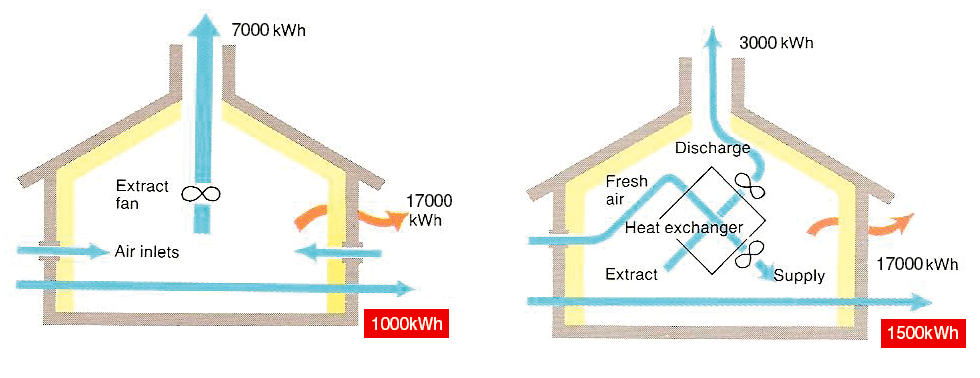
図3(排気型換気システム)と図4(熱回収型換気システム)の建物をご覧ください。
注目すべき点は「建物の隙間で発生する自然換気熱損失量」です。排気型換気システムよりも熱回収型換気システムを取り付けた建物の方が、年間の自然換気損失量は1・5倍にもなってしまうのです。
したがって、熱回収型換気システムを採用する建物は、現在の日本の気密基準よりもはるかに厳しい気密が既に要求されていたのです。
北欧の住宅用換気史から分かる知恵と経験の流れをまとめると、次のようになります。
「自然換気」主流の60年代
↓
「排気型換気か、またはその排熱を水に回収する装置付き」「全熱および顕熱交換換気」が乱立の70年代
↓
「顕熱交換換気」全盛「全熱交換換気」が消滅の80年代
↓
「換気システムの給気ダクト汚染(詰まりではなく、フィルターやダクト内面の不衛生)」対策の法制強化がされた93年
↓
「排気型セントラル換気システム、またはその排熱を水に回収する装置付き」の90年代以降
先進国は90年代に入って反省期に入り、70年代の省エネルギー住宅+24時間換気システム方式に戻った現実があります。
換気はダクトシステムが最善だということに変わりはない

・排気バルブの例
現在は、換気扇を何個もつける考えや、トイレや浴室、クローゼットなどの排気を換気扇で行い、給気を熱交換型セントラルダクトシステムで行うハイブリッド型がありますが、このような中途半端な方法は、以前のストーブを各室に配置する考えと同じで空気量のコントロールには不適と言えます。
また、セントラルダクト方式でも、排気口を床上に上向きで取り付けるのはゴミを吸引するので避けなければいけません。
・排気バルブの取付場所
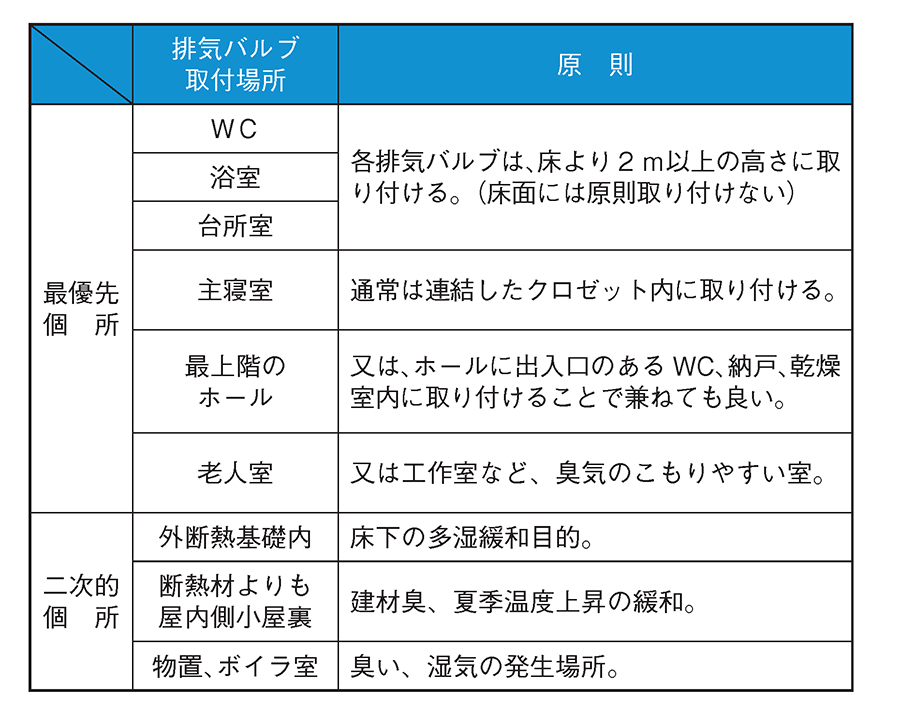
さらに、排気バルブを各居室にまで取り付ける手法も、肝心の汚染室(トイレ、浴室、台所室など)の排気が少なくなってしまうので避けることが賢明です。給気と排気の位置は明確に区分されるのが原則であり、例外はごくわずかな理由のときに限られます。
例として、古くから現在まで変わっていない北欧の換気システムのスパイラルダクト配置概要を、図5と図6に示します。
どちらの換気システムでも、排気バルブを取り付ける場所は、浴室・WC・台所・CL(クローゼット)であり、居室には原則取り付けません。
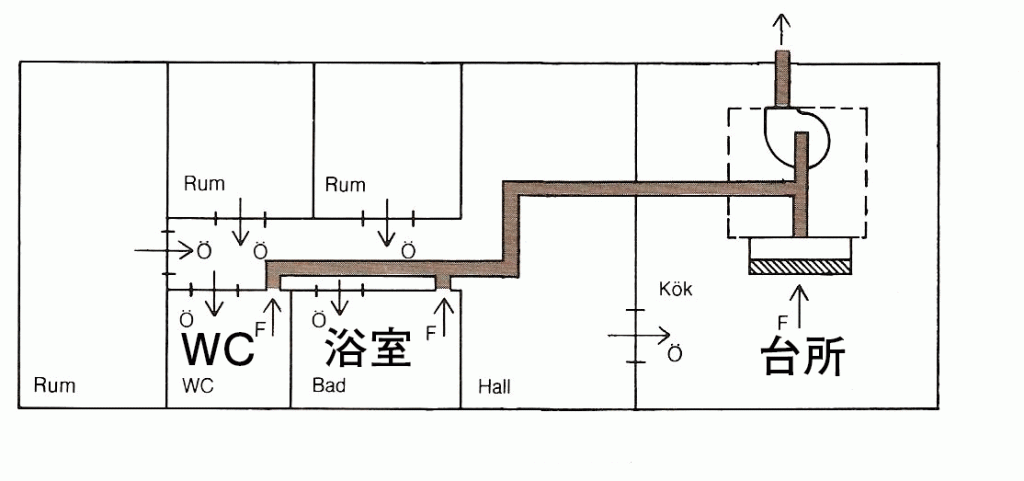
図5 排気システム
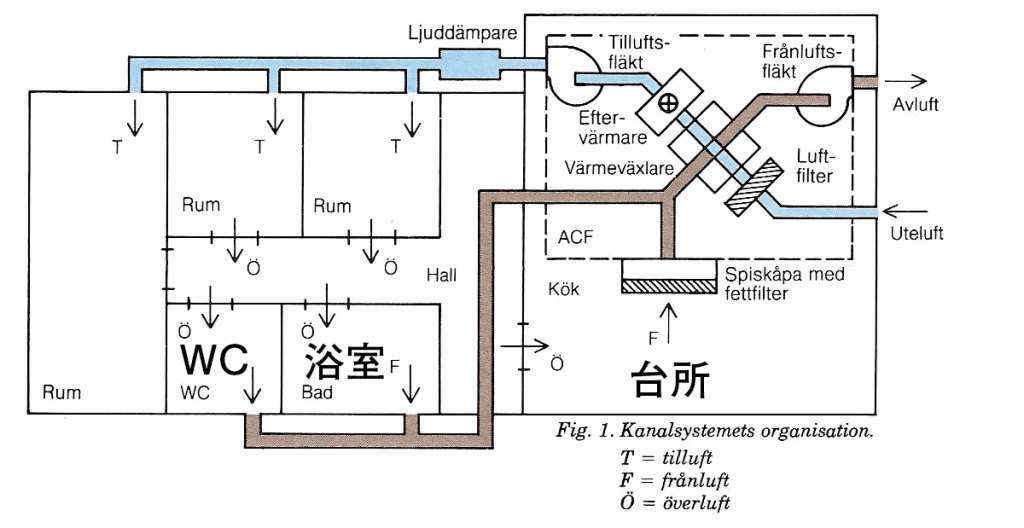
図6 熱交換システム
エコやCO2削減は高くつく
先に、熱交換換気装置やヒートポンプ装置が、エコだとかCO2削減だとか言い出した昨今よりもずっと昔からあったということ、そして高効率熱回収の製品も30年近く前から存在していたということを皆さんにお伝えしました。
それがなぜ今さら、省エネ住宅の設計に役立つと引っ張りだされているのでしょうか? 答えは簡単! CO2削減の数値を他国に示したい自国の役人、それに伴ってビジネスに利用できると考える企業群やグループが存在するからです。
最近の日本では、熱回収型換気システムの熱回収量のみ見て(購入費や運転経費の増大には目を向けず)、換気負荷計算上で建物の熱損失値(Q値)が少なくなるという、まったくばかげた机上計算がなされ出しました。
ユーザーは、見かけに飛びつかず、新型にのめり込まず、本当に価値のあるものを理解する眼力がますます必要となることでしょう。
・熱交換器の有効性(利用率)
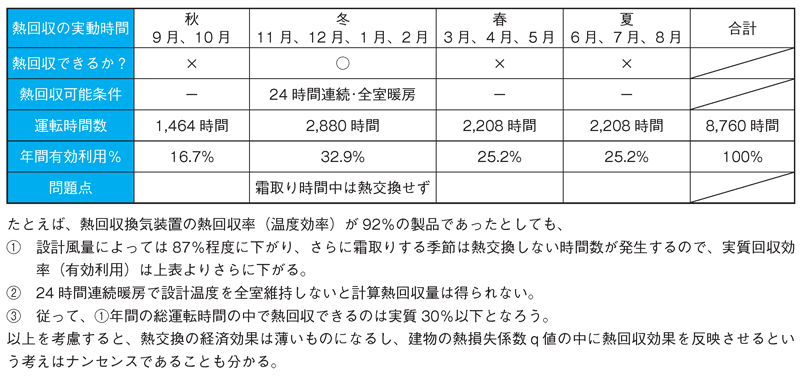
快適性と安全性を得ながらトータルコストを低減
安ければよいということと、建築基準法の審査さえ受けられればよいということでパイプファン(換気扇)が国内でわが世の春をおう歌しています。単純な換気扇が年間1200万個も日本で売れるようになったとか。
でも、最低基準しか要求しない法律を守ることと、住宅内部の衛生をきっちりと保つことは、まったく別次元の話です。
大手家電メーカーの24時間対応換気扇を購入して、実際の建物に取り付けて風量測定をしてみたものの、換気風量はカタログ表示通りに確保できていませんでした。このことに一般のユーザーの方はどれくらい気づいているのでしょうか。
前述した新型エコ商品も高価なものです。ヨーロッパのボイラーのように、40年間以上の耐久性がなくては採算に合いません。そのためには、部品も各社共通の規格にするべきでしょう。それができなければ、昔から使われてきて性能の安定した、簡単な構造の空調システムを選ぶ方が利口というものです。
新型という名のもとに、広告宣伝で購買意欲をかき立て、ヒット商品が出れば出るほど、それに伴う資源消費と生産行為・運搬行為、取り付け作業行為などでのエネルギー大量消費と、廃品排出による環境汚染を招きます。
家も商品も、部品点数やIC回路の少ない、そして各企業同一規格の丈夫な建物や製品を造り40年は持たせる、そして消耗部品も供給し続けることの方が、ずっと環境にやさしく、将来後悔しないのではないでしょうか。
北海道暖冷房換気システム協会発行・北暖協NEWS第18号掲載原稿を一部変更